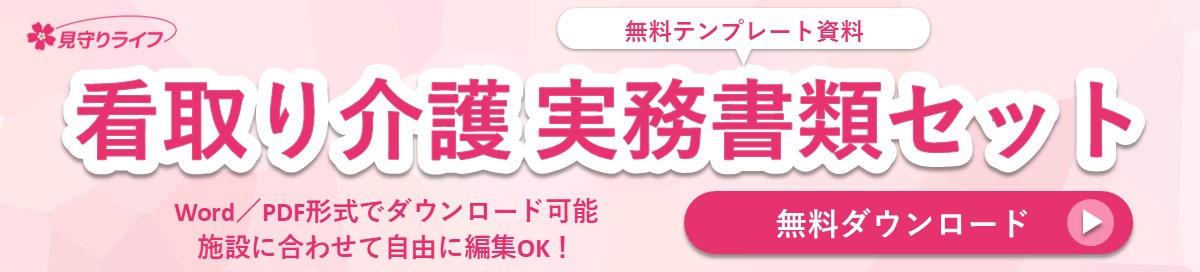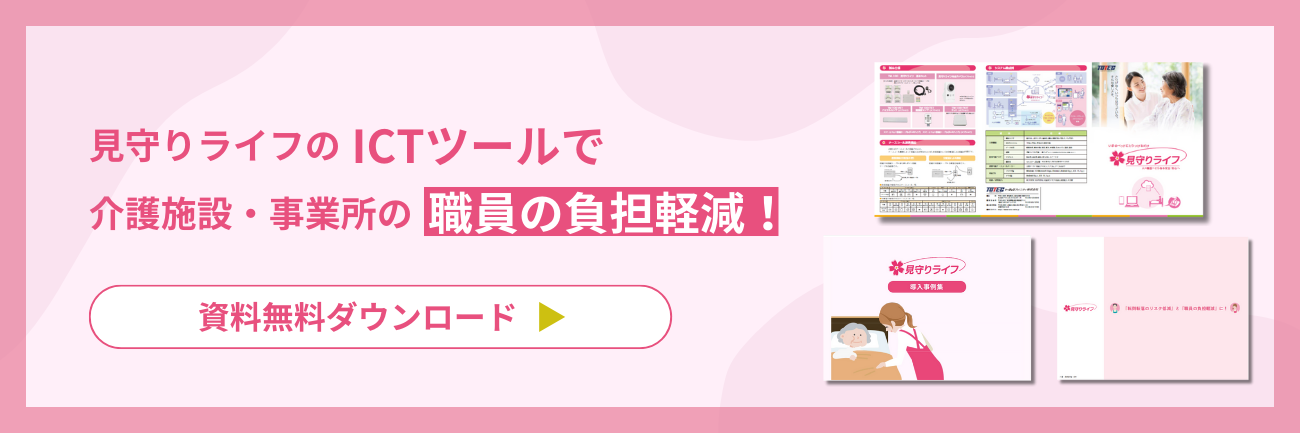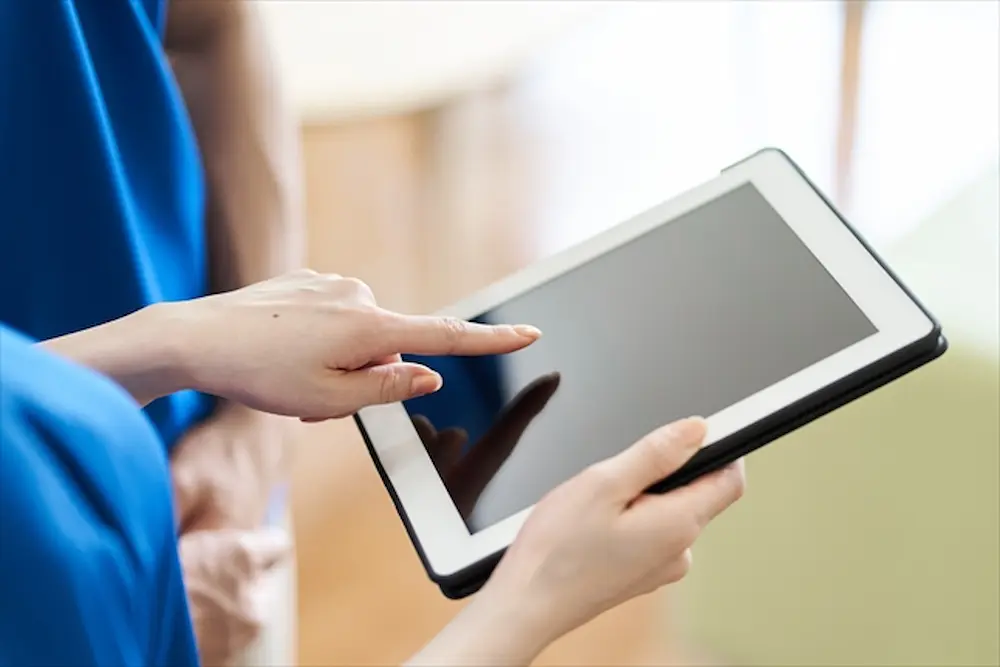記事公開日
最終更新日
看取り後の職員のケア 「グリーフケア」「グリーフシェア」とは

「このまま仕事に戻って大丈夫なのかな…」 利用者様を看取った直後、そんなふうに感じたことはありませんか? 介護職にとって“看取り”は、ただの業務ではありません。最期の時間を共に過ごし、声をかけ、見届ける…。その重みは、心にじんわりと残ります。 けれど現実には、次の業務がすぐに待っています。 悲しみを受け止める時間も、言葉にする余裕もないまま、自分の気持ちをしまい込んでしまう。 そんな職員の“心の消耗”を防ぐために、いま必要とされているのが「グリーフシェア」という考え方です。
グリーフ(悲嘆)とは
介護の現場で避けられないのが、「看取り」や「死」と向き合う時間です。利用者様との別れは、職員にとっても深い喪失体験であり、「グリーフ(悲嘆)」という心のプロセスが始まります。
「グリーフ」とは、大切な人やものを失ったときに感じる自然な感情反応のことを意味します。グリーフ(grief)という言葉は、ラテン語の「gravis」(重い)から派生した古フランス語の「grief」(悲しみ)に由来します。
グリーフ(悲嘆)とは、大切な人やものを失ったときに生じる自然な心理的反応です。単なる「悲しみ」や「落ち込み」とは異なり、身体的・心理的・社会的・スピリチュアルな側面を含む複雑な反応であり、人それぞれ異なる回復のプロセスをたどります。
グリーフは単なる「悲しみ」ではありません。涙が止まらない、深い孤独感、食欲不振、不眠、集中力の低下などの身体的な影響や、同僚やご家族と距離を置きたくなるなど社会的な変化も含まれます。心の痛みは人それぞれ違い、その表れ方も時間も個人差があります。
介護職員の場合、長年担当してきた利用者様との別れや、日々の業務の中での喪失体験がグリーフのきっかけとなります。
「死を受け入れる」までの5つのステップ
心理学者キューブラー・ロスが提唱した「死の受容プロセス」は、グリーフの理解を助けてくれる代表的な理論です。これは、看取りを経験した家族だけでなく、支援する側の介護職員にも共通する心の動きとも言えます。
1. 否認(Denial)
「そんなはずがない」「まだ大丈夫」
現実を受け入れきれず、心を守ろうとする防衛反応です。
2. 怒り(Anger)
「なぜこんなことに」「どうして自分が」
行き場のない感情が、自分や他人に向けて噴き出します。
3. 取引(Bargaining)
「〇〇すれば助かるのでは」「もっと良くできたはず」
過去を悔いたり、もしもの未来にすがるような気持ちが現れます。
4. 抑うつ(Depression)
「何もできない」「喪失感に押し潰されそう」
深い悲しみが現実としてのしかかる時期です。
5. 受容(Acceptance)
「もう大丈夫」「ありがとうと言えるようになった」
穏やかな気持ちで、別れを自分の中に受け入れられる段階です。
ただし、これらのステップは順番通りに進むものではなく、前後したり、何度も行き来することもあります。 これは、故人を失うという大きな変化に対して、人間の心と身体が適用しようとする自然な反応です。 どの段階にあるかを知ることは、職員自身が自分の感情を客観的に見つめ、無理をせずケアしていく手がかりになります。
「グリーフケア」と「グリーフシェア」とは
「グリーフケア」と「グリーフシェア」は似ている言葉ですが、アプローチの対象や視点が異なります。
グリーフケアとは
死別や喪失を経験した人が、悲しみの中で少しずつ心を整理し、再び自分らしく生きていけるよう支援することを意味します。専門職(カウンセラーや僧侶、看護師など)が行うケアもグリーフケアに含まれると言えるでしょう。
介護現場では、遺族に対するケアや、亡くなった方との関わりをふりかえる儀式などもグリーフケアに含まれます。亡くなられた利用者のご家族だけでなく、施設職員に対しては、心理的なケアや面談、勤務調整などがこれにあたります。
グリーフケアの対象は悲嘆(グリーフ)を抱えている人(利用者・家族・職員)であり、誰かが誰かをケアするという構図です。
無理に気分を変えようとせず、「話したいときに話してもらう」「思いを否定せず受け止める」といった関わり方が大切です。たとえば、「まだ気持ちの整理がつかないのは自然なことですよ」と伝えるだけでも、安心感につながります。
グリーフシェアとは
グリーフケアに対してグリーフシェアは、立場に関係なく「悲しみを共有すること」そのものを指します。ケアする」「される」ではなく、共に分かち合うという対等な関係性です。
スタッフ同士で亡くなった利用者さんの思い出を話す時間も、れっきとしたグリーフシェアにあたります。
「慰めよう」「元気付けよう」という目的ではなく、「ただ感じた事を言葉にする」「誰かが受け止めてくれる」という安心感のもと、感情を表に出せる時間をもち、悲しみとを共有します。
グリーフシェアの対象は悲嘆(グリーフ)を共有しあえる関係者(主にスタッフ同士)であり、役割や肩書きではなく、感情を分け合うことが主軸になります。
介護職員は“支える側”でありながら、自分自身の悲しみに蓋をしてしまいがちです。しかし、グリーフを抱えたまま、いつも通りの業務をこなすことはとても難しいものです。人の心は「誰かと悲しみを共有すること」で少しずつ癒されていく力を持っています。
それが、「グリーフシェア」という取り組みです。
なぜ「グリーフシェア」が必要なのか
看取りに携わるスタッフは、単に「死」扱うのではなく、「人の人生と向き合う」仕事です。 その感情を一人で抱え続けることは、スタッフ自身の働く熱意や意欲を奪い、退職の一因になることもあります。グリーフシェアは、「職場の中で思いを言葉にできる場」、「誰かが受け止めてくれる環境」をつくり、感情を溜め込まずに次のケアへと向かうサポートになります。
喪失を語ることが、心の整理につながる
誰かに話すことで、あいまいだった感情に名前がつき、自分の中で受け止めやすくなります。
一人で抱え込まない文化が、離職防止にも
感情が限界を迎えて離職してしまうケースも、グリーフを職場で支え合うことで回避できます。
職場の仲間が“わかってくれている”という安心感
悲しみの中でも、孤独ではないという実感が、次のケアへの力をくれます。
グリーフシェアはどう実施するか

看取りのあとに「ふりかえりの時間」を設ける
短時間でも、「○○さんらしかったよね」「最後は穏やかでよかった」と語る場が、心の支えになります。
チーム内で、気になる職員に声をかける習慣を
「大丈夫?」よりも、「私も寂しかったよ」のように、共感を添えた言葉が効果的です。
月1回などのミニケースカンファレンスで感情も共有できる時間を設ける
看護や介護の視点に加え、「どんな想いで寄り添ったか」まで話せると、ケアの質も高まります。
また、悲嘆には「正常な悲嘆」と「複雑性悲嘆(悲嘆反応が長引く状態)」があります。正常な悲嘆は時間とともに和らいでいきますが、長期間強い悲しみが続き日常生活や仕事に支障をきたす場合は、専門的なサポートが必要になることもあります。自分や仲間の変化に気づいたら、早めに相談することも大切です。
「グリーフ」をチームで抱え、乗り越えるという姿勢は、介護職のメンタルヘルスを守るだけでなく、結果的に利用者様へのケアの質も上げてくれます。 「心に余白があること」こそが、寄り添うケアの土台なのかもしれません。
まとめ
「慣れたら楽になる」と言われても、人の死に慣れることなんて、本当はないのかもしれません。
看取りの現場は、命の重みと向き合う場所です。だからこそ、別れのあとに生まれる感情を職場で大切にしていくことは重要なのだと思います。
スタッフが心を閉ざさず、感情を置き去りにせずに働き続けられるように。 施設全体で「悲しみも話していい」空気をつくることが、安心・信頼のチームづくりにもつながります。
グリーフシェアは、特別な知識や資格がなくとも誰にもできる心のケアの第一歩です。スタッフ一人ひとりの「感じた気持ち」に、耳を傾けることから初めてみませんか。
▼こちらの記事もおすすめです
▼見守りライフについて詳しく知りたい方はこちら