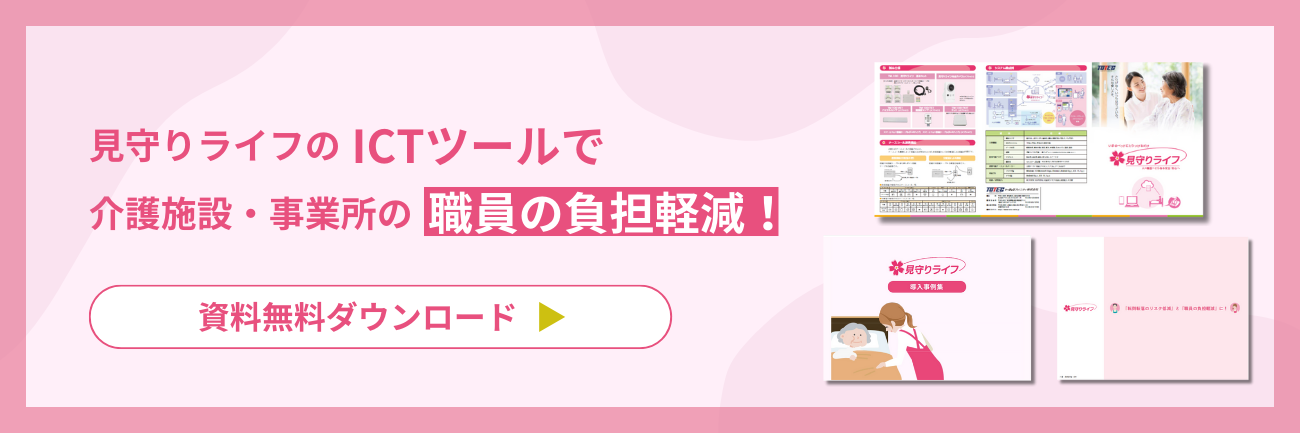記事公開日
最終更新日
高齢者の徘徊に安心と希望を!介護事業者が実践する予防と対処の方法

徘徊は高齢者や家族にとって大きな悩みです。介護事業者として、徘徊する高齢者にどのように寄り添い、安心と希望を与えることができるのでしょうか?徘徊の原因と予防方法、緊急時の対処と見守りシステムについてご紹介します。
1.高齢者の徘徊に寄り添う介護事業者の使命とは
徘徊は認知症を抱える高齢者にとって一般的な行動であり、その理解が事業者にとって不可欠です。認知症は誰もがなりうるものであり、家族や身近な人が認知症になることを含め、多くの人にとって身近なものになっています。徘徊の背後には様々な要因がありますが、個々のケースに対応するには高齢者の心理を深く理解することが重要です。徘徊は過去の環境に戻りたいという欲求から生じることがあります。これを踏まえ、特養・老健の事業者は個別の対応策を検討し、高齢者の心に寄り添ったサービスの提供が求められます。
徘徊行動は、高齢者が過去の記憶や慣れ親しんだ環境を求める心理的な反映であることが多いです。例えば、子供時代の家を探す、若い頃の職場に行くなど、過去の重要な場所や人々に対する強い思い出が徘徊のトリガーになることがあります。これらの行動は、高齢者が現在の環境や状況に満足していない、または何らかのストレスや不安を感じているサインである可能性があります。
また、目的があって外出したものの道がわからなく なってしまうなど、本人なりの理由があっての行動である点も重要です。安心して自分らしい生活を送りたいという願望は高齢者共通の要望であり、特養・老健の事業者はこれを踏まえたケアプランの構築が求められます。支援が必要な高齢者とその家族との対話を通じ、信頼関係を築き上げ、徘徊に関するリスクを最小限に抑える方策を検討しましょう。
家族の心理とニーズを理解する
高齢者の家族もまた、徘徊によるリスクに対して不安や悩みを抱えています。事業者は家族の心理とニーズを理解し、適切なサポートを提供することが求められます。家族はしばしば、徘徊に対して心の負担を感じています。このため、事業者は家族とのコミュニケーションを大切にし、情報共有を進めることが必要です。
具体的な支援として、定期的な相談会や情報提供を通じて家族をサポートすることが考えられます。家族と協力して課題に取り組む姿勢が求められます。事業者が家族の立場に立ち、共感と理解を示すことで、安心感を提供し、協力体制を構築できるでしょう。
2.徘徊の原因と予防方法の実践例
徘徊を繰り返し、施設を飛び出して転倒したり交通事故に遭った結果、最悪の場合亡くなってしまう危険性があります。その結果、介護事業者が損害賠償責任などの法的責任を追及されることもあります。
過去に実際、非常口から施設を抜け出し、低体温症により亡くなった事故や1階の窓から脱出して行方不明となり後日、亡くなった状態で発見された事故がありました。どちらの事例も職員に対し過失があると判断され、介護事業者は賠償責任を求められました。
介護事業者は徘徊の原因を深く分析し、それに基づいた予防計画を策定する必要があります。認知症における徘徊は様々な要因から生じるため、一概には対処できません。徘徊の原因を理解し、個別の事例に合わせた対策を講じることが求められます。
徘徊のサインを見逃さず、適切な介入を行う
徘徊の原因は個別性が強く、同じ症状でも背後にある要因は異なります。介護事業者としては徘徊の発端となる要因を慎重に分析し、個別化した予防計画を立てることが重要です。例えば、徘徊が過去のトラウマに基づくものであれば、専門的な心理的支援が必要です。計画は柔軟性を持たせつつも、徹底的なサポートを提供し、高齢者が穏やかで安心な環境で過ごせるよう努めましょう。
徘徊のサインを見逃さず、適切な介入を行うことは認知症の高齢者の安全と生活の質を向上させる重要な要素です。
認知症患者の徘徊に関するサインは様々です。例えば、外出時に戻るのが難しい、同じ場所を繰り返し歩く、特定の場所や人物に興味を示すなどが挙げられます。これらのサインを見逃さず、スタッフは常に高齢者の行動を注意深く観察する必要があります。
見逃しやすいサインに対処するために、職員への教育とトレーニングが欠かせません。徘徊に関する知識を共有し、特に初期のサインに敏感に反応できるようにすることが重要です。また、家族や関係者からの情報も取り入れ、総合的な視点でサインの把握を図ります。
介入には言葉でのサポートやリラックスした雰囲気づくりが重要です。徘徊をする方の中には、仕事に行く、家に帰るなどの目的をもって徘徊していることがあります。こうした場合は「今日はもう遅いから明日にしては」などの理由を述べて優しく接します。次の日には忘れてしまうケースが多いため、毎日同じ対応でも効果があります。高齢者に安心感を与え、徘徊行動を防ぐためには、ケアのプランに基づいたコミュニケーションが欠かせません。また、適切な見守りシステムの導入や活用も効果的です。
徘徊のサインを検知した場合、迅速な介入が求められます。事業者は定期的なチームミーティングや報告システムを通じて情報共有を行い、スタッフ全体が連携して対応できるようにします。介入の方法は個々の状況に応じて柔軟に変化し、高齢者の安全確保を最優先とします。 安全を確保する努力が重要です。
生活の質を向上させるための工夫
徘徊が生じた場合でも、特養・老健の事業者は高齢者の生活の質向上を図るべく工夫が必要です。つまり、高齢者が安心して自分らしい生活を送れるように、特養・老健の事業者は居住環境の改善に努める必要があります。
例えば、施設内での安全な徘徊スペースを設けることで、高齢者が安心して移動できる環境を提供できます。また、趣味や嗜好に合わせたアクティビティを導入することで、徘徊が活動的な時間となり、生活の充実感が増すでしょう。

3.対処と見守りシステムの実践例
施設を飛び出してしまったなどの緊急時の介入においては、徘徊した高齢者の捜索活動をすみやかに開始し、同時に警察や地域の協力を得ることが不可欠です。家族への連絡も迅速に行う必要があります。そのようなことが起きないためにも以下の方法が有効的です。
徘徊時の捜索と探知システムの導入と活用
徘徊の結果、利用者が行方不明になるリスクは避けるべきです。事業者は緊急時の対処として捜索と探知システムの導入を検討し、これを活用することが求められます。GPSを利用したトラッキングデバイスや防犯カメラの導入など、最新の技術を取り入れることで、利用者の安全確保に繋がります。
安全確保と事故防止のための工夫
徘徊の高齢者の安全確保と事故防止のためには、介護事業者は慎重な工夫が求められます。まず、施設内の環境設計において、高齢者が安心して移動できるような配置や案内システムの導入が欠かせません。明確で分かりやすいサインや地図を活用し、徘徊を防ぐ工夫が必要です。
ベッドを離れた際に職員に伝える「見守りシステム」は、さまざまな種類があります。床に敷くマットタイプや赤外線で反応するタイプ。壁などに設置しカメラで検知し通知するカメラタイプ、マットレスの下に敷き状態を判定するバイタルタイプ、ベッドの脚の下設置する荷重センサータイプと様々あります。
見守りライフは、荷重センサータイプであるため、誤報が少なく、検知スピードが速いのが特徴です。ベッドから離れて長時間戻っていない場合に通知する機能もあります。さらにベッドへ戻った際の通知も可能です。さらにカメラ機能もあるため、居室だけでなく施設の廊下部分に設置し状況を確認することもできます。
見守りシステムの他には、徘徊センサーやエリア検知システムも有効です。利用者にICタグや送信機を身につけてもらい施設の出入口等に設置したセンサーが反応し通知がいくシステムです。
徘徊の予兆を早期に検知するために、センサーや監視カメラの利用が効果的です。これらの技術を駆使して、高齢者の動向をリアルタイムで把握し、徘徊が始まる前に介入できるようにします。同時に、徘徊のリスクが高い利用者にはGPSを活用した位置情報システムを導入し、外出時の安全確保にも努めましょう。
また、事故防止のためには、障害物の除去や手すりの設置などの環境整備が欠かせません。高齢者が転倒しにくい床の採用や、非常時に備えた訓練も行うことが必要です。スタッフは日常的な巡回やモニタリングを通じて、危険な状況を早期に発見し、適切な対応が必要です。
徘徊の発生リスクが高い場合、個別のケアプランを策定し、家族や関係者との密な連携を図ります。事業者はこれらの工夫を通じて、高齢者が安全かつ快適に過ごせる環境を提供し、事故のリスクを最小限に抑えることが期待されます。
4.まとめ
徘徊の高齢者に寄り添う特養・老健の事業者は、その役割と責任を重要視しなければなりません。高齢者とその家族の心理とニーズを理解し、徘徊の原因と予防方法に的確にアプローチすることが求められます。また、緊急時の対処と見守りシステムの活用により、高齢者の安全確保を徹底的に行い、生活の質向上に尽力することが不可欠です。
徘徊の原因と予防方法、見守りシステムの活用は事業者にとって継続的な課題です。これらの側面を適切に管理し、従業員と協力して徘徊の高齢者に安心と希望を提供することは、地域社会において重要な介護施設の使命でもあるでしょう。