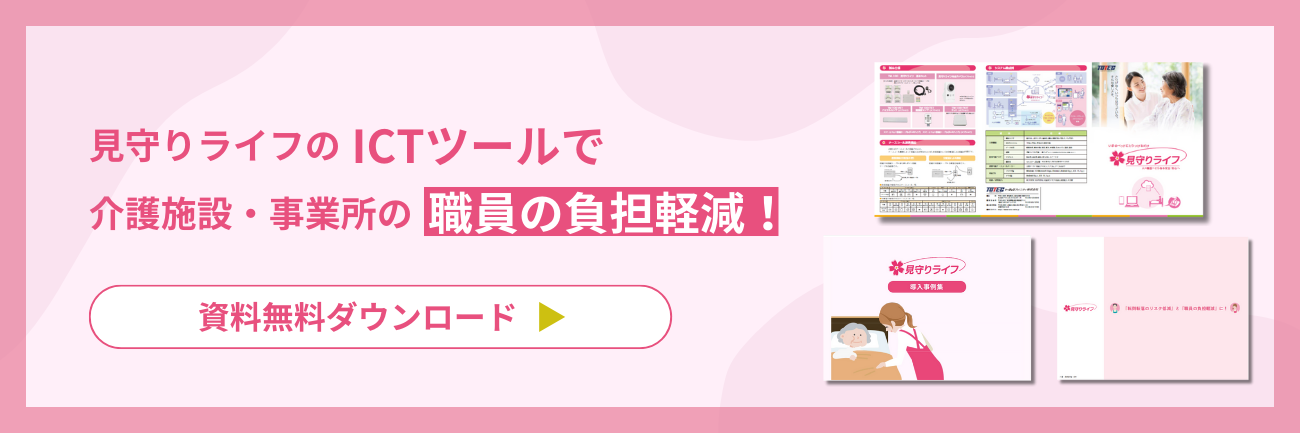介護業界が抱える課題とは?原因と対策を徹底解説

昨今では超高齢化社会の影響を受け、介護業界で働く人材の需要が高まっています。 しかしながら、介護職員が少ないという状況が慢性的に続いており、これからさらに需要と供給の差が広がっていくことが予想されています。
本記事では、介護業界が抱える課題と課題解決に向けた取り組みについて詳しく説明していきます。 介護サービスの利用者数に対して働き手が少ないといった課題が深刻化しているため、国の対策や介護業界の事業方針の行方に注目です。
サービスサイトはこちらから
介護業界の最大の課題とは?
介護業界の課題は多岐にわたり、人口の推移や介護事情の詳細を見ると深刻な状況です。 市場規模が大きくなり将来性が高いことは間違いないですが、増えすぎた需要に供給が間に合っていません。
では、具体的にどのような課題を抱えているのか見ていきましょう。
迫り来る超高齢化社会、2025年問題
2025年問題とは、1947年〜1949年の第1次ベビーブームで生まれた「団塊世代」全員が、75歳以上の後期高齢者になることで起こる問題です。
内閣府が公開している「平成29年版高齢社会白書」によると、全国の高齢者人口は2016年時点で3,459万人、2025年には3,677万人となり総人口に占める65歳以上の割合(高齢化率)は30%に達するとされています。
その後も高齢者人口は増加傾向が続き、2042年に3,935万人でピークを迎え、その後は減少に転じると推計されています。 総人口が減少する中で高齢者が増加することにより高齢化率は上昇を続け、2036年に33.3%となり、2042年以降は高齢者人口が減少に転じても高齢化率は上昇傾向にあり、2065年には38.4%に達する見込みです。 国民の約2.6人に1人が65歳以上の高齢者となり、約4人に1人が75歳以上の後期高齢者となると推計されています。
また、認知症高齢者数の見通しとして、2012年の時点では約462万人ですが、2025年には約675万人になると推計されています。
これらの推計からも、若者や介護する方の負担が今後さらに大きくなるのは間違いありません。 高齢者のいる世帯は2015年時点で、2372万4千世帯と、全世帯(5036万1千世帯)の47.1%を占めています。 また、一人暮らしをする高齢者も増加傾向にあり、2015年時点では約592万人が一人で生活をしており、孤独死する方も出てくるでしょう。
参照元:平成29年版高齢社会白書(概要版),平成29年版高齢社会白書(全体版)
介護における日本の社会問題
2025年問題の影響を大きく受ける業界のひとつが介護業界です。65歳以上の割合が全人口の21%以上を占める超高齢化社会の到来により、社会全体で取り組まなければならない課題が多くあります。
では、具体的に介護における社会問題にはどのようなものがあるのかを見ていきましょう。
高齢者の一人暮らし
高齢者の一人暮らしは近くで介護してくれる家族がいない状況なので、認知症や介護度が自覚のないままに進行していたり、犯罪などのトラブルに巻き込まれやすくなったりなど様々なリスクがあります。
一人暮らしの理由は、配偶者に先立たれた、熟年離婚をしている、現時点で経済的・健康面などの不安を感じない、そもそも独身者…などが考えられます。
元気なうちは一人暮らしでも問題がなかったとしても、高齢になるにつれて介護が必要な状況になる可能性が高くなるでしょう。たとえば食事・排泄・入浴は一人で問題なくできたとしても、掃除やゴミ出し、洗濯など身体的に負担の大きい家事が困難になってきます。
自力で難しいことがある場合は、介護保険サービスや自治体による支援サービスなどを活用するなどを考える必要があります。
また、住宅をバリアフリーにするなど高齢になっても過ごしやすい環境にすることも求められるでしょう。
介護人材の不足
超高齢化社会が進んでいく昨今、少子化の社会問題もあることで介護人材の不足が課題になっています。 介護人材が不足すると職員一人あたりの負担が大きくなり、増えていく高齢者の介護に対応できません。
厚生労働省は介護職員の不足数について2040年度に介護職員が約280万人必要となり、現状から試算すると69万人が不足すると推計をだしています。
参照元:第8期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について
介護職員の年齢構成は30〜49歳が主流になっていて、訪問介護では60歳以上が約3割を占めています。 ゆくゆくは介護職員が高齢になって、介護現場の負担が大きくなるでしょう。
また、介護分野における人材確保の状況と労働市場の傾向は、2008〜2010年の間が大きな転換期でした。 介護職の失業率は2010年から低くなってきていますが、有効求人倍率は上昇傾向にあり2016年時点では3.02倍でした。
全職業の有効求人倍率1.36と比較すると、人手不足が深刻であることがうかがえ、これからも大きな課題になるでしょう。
参照元:厚生労働省公式HP社保審一介護給付費分科会(第145回H29.8.23)「介護人材確保対策(参考資料)」
地域ごとの状況を見てみると高齢化の状況に大きな差があり、都市部では急増、地方はゆるやかに増加すると見込まれています。 たとえば75歳以上の人口において、2010年で58.9万人もいる埼玉県は、2025年で117.7万人になるといわれていて、その数は約2倍です。 地域によっては約1.1倍と微増のところもあるので、対策の仕方は自治体によって異なるでしょう。
老老介護・認認介護
一緒に暮らす家族が高齢の場合、親を介護するのが一般的ですが、現代では高齢夫婦がお互いを介護する「老老介護」が課題になっています。 また、加齢によって認知機能が低下して、認知症患者同士が介護をする「認認介護」も増加するのも大きな課題です。
そこで、2012年9月の「認知症施策推進5か年計画(オレンジプラン)」によって課題解決の動きが起きました。
内容は「認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けることができる社会」の実現を目指すため、新たな視点に立脚した施策の導入を積極的に進めることです。
具体的には以下の7つの施策が行われ、2013年〜2017年までの5年間で必要な医療や介護サービス等について数値目標を定めて整備を図ります。
1. 標準的な認知症ケアパスの作成・普及
2. 早期診断・早期対応
3. 地域での生活を支える医療サービスの構築
4. 地域での生活を支える介護サービスの構築
5. 地域での日常生活・家族の支援の強化
6. 若年性認知症施策の強化
7. 医療・介護サービスを担う人材の育成
社会全体で認知症の人々を支えるように、介護サービス以外でも地域の自助・互助を活用していくことが重要です。
参照元:厚生労働省公式HP社保審一介護給付費分科会(第115回H26.11.19)「認知症施策の現状について」
ヤングケアラー問題
ヤングケアラーとは、一般に、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている18歳未満の子どもとされています。
年齢や成長に見合わない負担をかけてしまうと、子どもの育ちや教育に影響が及びやすいです。 家族を支えて助け合うことが問題ではなく、健やかな成長と教育の機会が奪われてしまうことが問題視されています。
厚生労働省の実態調査結果によれば、調査対象である全国の923自治体の各市区町村の要保護児童対策地域協議会のうち、「『ヤングケアラー』と思われる子どもが1人以上いる」のは、341自治体(2,174件)にも上ります(令和元年度実績)。
このうちのすべてが介護に関わっている子どもとは限りませんが、把握し切れていないヤングケアラーが存在することを考慮すると、見逃せない問題です。
参照元:令和2年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「ヤングケアラーの実態に関する調査研究報告書」厚生労働省
社会保障の財源不足
日本の介護における問題として、社会保障の財源不足があります。
財源不足は国の一般会計歳出の約3分の1を占めるほどの規模で、大きな課題です。 基本的に消費税や所得税などの税金が原資になっていますが、少子高齢化と超高齢化社会は財源不足に大きな影響を与えています。
財源不足の原因は、少子高齢化で労働人口が少なくなり、現役世代である納税者が減少していることにあります。 さらに、高齢者が増加しているので、社会保障費は増大しているため、財源不足が悪化しています。最終的に借金(国債)に頼る分も増えていて、社会保障をまかなっているのは税金と借金です。 負担する費用は年間1兆円規模ともいわれており、社会保障費は今後も増えていくことでしょう。
「75歳以上人口の増加と1人当たり医療費・介護費」を確認すると、65〜74歳の費用の負担が急増します。たとえば2019年の医療における1人当たりの国庫負担は65〜74歳までで8.0万円ですが、75歳以上になると約4倍の32.4万円です。 他にも介護における1人当たりの国庫負担は65〜74歳までで1.3万円で、75歳以上になると約10倍の12.7万円になります。
介護業界が抱える課題
ここまでは、介護における日本全体の問題を解説しましたが、ここからは介護業界の課題を説明します。
深刻な介護人材不足
介護業界が抱える課題の1つとして、人材不足があります。 人材不足の原因は「需要と供給のギャップ」「給与・待遇が良くない」の2点が挙げられています。 根本的な解決として、介護業界で働く人たちが満足できる環境づくりが成功すれば、人材が集まって課題をクリアできるでしょう。
では、具体的な課題を1つずつ見ていきましょう。
需要と供給のギャップ
厚生労働省が2015年6月に発表した「2025年に向けた介護人材にかかる需給推計(確定値)について」を見ると、2025年で需要が253万人で供給が215万人、約38万人の介護人材不足が予想されており、介護業界の人材不足は深刻な状況です。 生産年齢人口減少等による供給量の減少によって、需要との差がどんどん開いているのが現状です。
参照元:「2025年に向けた介護人材にかかる需給推計(確定値)について」
供給が需要に追いつくように「総合的な確保方策」による押し上げを図っており、5つの主要施策を行っています。 主要施策の目的は、介護業界の参入促進、労働環境・処遇の改善、資質の向上です。
現状は専門性が不明確になっていて、仕事の役割が混在しています。そのため、将来の不安で早期退職につながり、需要と供給にギャップがあるというのが課題です。
そこで、介護の人材を細分化して、専門性の高い人材と基礎的な知識を有する人材に分けることがポイントになります。国が法令を出し、地域が予算を出して協力的に施策を行っていく方針です。
法令として、国は介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するために、令和2年2月に「基本指針」を定めました。これを受けて、地域の関係主体が協力して予算を出し合うことで、人材確保のプラットフォームを創設する流れです。
参照元:「基本指針について」厚生労働省
給与・待遇が良くない
構造的な問題として、介護業界は介護保険制度によって給料の上限が決められているという課題があります。つまり、一般企業に勤めていると徐々に給料が上がりますが、介護業界は上限に達してしまうと、それ以上は上げるのが難しいのです。
さらに詳しく説明すると、老人ホームの利用が1日いくら、訪問介護でいくらなど報酬単価が決められています。給与を自由に上げられないのが人材不足の要因の1つです。やりがいも重要ですが、あまり稼げないという事実を知ってしまうと、転職で職種を変えるなど人材が他業種に流れてしまいます。
介護職員の賃金は、介護事業所の収入から支払われています。介護保険サービスを提供している場合、介護事業所の介護報酬として扱われます。
サービスの利用者数当たりの職員の数が施設ごとに定められているため、職員が不足していると介護サービスの提供はもちろん、人件費の削減も難しくなります。介護事業者が利益を出すには作業の効率化、経費の削減、稼働率をどれだけ最大に近づけられるかが重要です。
過酷な労働環境
介護業界の労働環境は過酷で、仕事のやりにくさや大変さがあります。
原因は「人手が足りないから日々の業務が終わらない」「休憩が少ない」などです。
業務は食事や排泄、衣服の着脱など多岐にわたり、掃除や洗濯などをしながら、日常生活が自力でできない方を常に見守り、サポートしなければなりません。
入所系の施設勤務になると夜勤があり、日勤よりも少ない人員で勤務します。入居者の体調の急変など緊急の対応が必要になるケースもあるので、油断できません。身体的にも精神的にも疲れやすくなり、集中力が低下してミスが重なりやすくなります。少ない人数で夜勤を回すこともあり、ペアによってはストレスを感じる方もいるでしょう。
また、夜勤は介護業界に限らず、仕事が忙しい、生活習慣のバランスが崩れるなどのイメージをもつ方も多いのではないでしょうか。そのため、募集をかけても応募する方が少なく、応募してきた方を採用しても過酷な労働環境で辞めてしまうケースが少なくありません。
介護難民
介護難民とは、介護サービスをしてくれる方がいなくて困っている方を指します。原因は、介護難民の増加(需要)と介護施設や人材の不足(供給)のバランスが取れていないからです。
内閣府が公表した「高齢社会白書(平成29年版)」によると、65歳以上の高齢者が年々増加しています。要介護・要支援認定者も増加していて、介護施設の入居待ちをしている方が非常に多いです。厚生労働省が公表した「特別養護老人ホームの入所申請者の状況」では、2019年で特別養護老人ホームに入所申請したけど入所していない方は29.2万人もいます。民間介護施設なら入居待ちになるケースはほとんどありませんが、特養などの公的施設は入居待ちにより利用できるまでに比較的長い時間がかかる傾向にあります。
入居待ちにより介護サービスを受けられないと家族にも負担がかかります。状況によっては仕事を休職したり、遠方の実家で介護をするために退職したりするなどの選択を迫られることもあります。引っ越しの手続きや収入の減少などで、経済的にも影響が出るでしょう。
要介護度別認定者数の推移も年々増えていて、介護難民はこれからさらに増えていく見込みです。
参照元:内閣府「平成29年版高齢社会白書(全体版)」,厚生労働省「特別養護老人ホームの入所申請者の状況」
社会的評価の低さ
介護業界に勤めていると、社会的評価が他の職業よりも低く、軽視されがちです。その背景としては前述した「給与・待遇が良くない」「過酷な労働環境」といった要因があります。
介護士には介護の基礎的なスキルを身に着けられる「介護職員初任者研修」や国家資格である「介護福祉士」などがあるものの、資格がなくても働ける職業です。
対して医師は医師免許、看護師は看護師免許がないと働けない職業なので、比較された結果、社会的評価が下がっている面もあります。
課題解決に向けた取り組み・改革
介護業界が抱える課題を理解したところで、ここからはどのような取り組み・働き方改革がされているのかを見ていきましょう。
ここまでご説明したように現場では多くの課題を抱えており、人材が不足している状況のため、早急な対策が必要です。これからさらに増えていく高齢者に対応できるように、介護や福祉の仕事に従事する職員の業務体制やケアが重要になります。
業務負担の軽減
介護職員の業務負担を軽減できた事例として、介護ロボットや見守りセンサーなどの導入があります。介護サービスの利用者や職員の精神的・身体的負担を軽減できるだけではなく、人材不足の課題を解決できるのがポイントです。
さらに、厚生労働省が2012年3月に公表した「文書負担軽減や手続きの効率化による介護現場の業務負担軽減に関する調査研究事業(結果概要)(案)」によると、業務はかなり改善されています。たとえば業務を一部電子化することで、紙の保存をする必要がなくなりました。
他にも、インカムを用いた音声入力により、ケアをしながら介護記録を行えるようにすることで記録時間が週17時間も短縮した事例もあります。このような施策も労働環境、待遇改善につながるといえるでしょう。
参照元:厚生労働省「文書負担軽減や手続きの効率化による介護現場の業務負担軽減に関する調査研究事業(結果概要)(案)」
介護士のメンタルケア
介護の仕事は、介護サービスの利用者、職員同士の人間関係、過酷な労働環境などによってストレスが溜まっていきます。
時には業務が忙し過ぎて職員が業務の課題や自分の悩みを相談する時間がとれない場合もあります。そこで、課題解決に向けた取り組み・働き方改革として定期的な面談を設けてメンタルケアを行うと良いでしょう。
面談では悩みの相談だけではなく、業務の改善点や人間関係の詳細などを聞くことが大切です。業務の改善展は介護職員だからこそわかる視点で教えてもらい、非効率な部分を効率化すれば働きやすい環境になります。
また、リーダーなど上司とのコミュニケーションの場を設けることでお互いの考え方を理解でき、職員の心理的安全性を高めることにもつながります。業務を行う理由や目的などをしっかり説明すれば、納得して仕事に取り組めるでしょう。
人間関係でストレスを抱えている職員がいた場合でも、面談で相談に乗れるようにすれば体調を崩す前にメンタルケアが可能になります。個々の能力や状況をサポートする体制を充実させることは、能力をアップさせキャリアを形成する上でも必要といえるでしょう。
パワハラやセクハラなどは大きな問題なので、事実を確認して対応することも重要です。
長時間労働の解消
社会全体でもあてはまりますが、介護業界でも長時間労働は大きな課題です。
たとえば、平均介護度が高かったり、リーダーなどの役職で働いたりすると、仕事量が増えて長時間労働になります。特に長時間労働になるのが16時間勤務の夜勤です。夕方の16時30分~翌朝の9時30分まで勤務します。休憩が1~2時間になるので、就労時間は計17~18時間になることが多いです。
最低限の人員で夜勤をまわしている場合、十分な休憩が取れないこともあり職員の負担が大きいため、勤務体制を見直すなどしっかり休憩や仮眠がとれる環境を整える必要があるでしょう。
とある施設ではマスクの色を夜勤と日勤で変えたり、夜勤勤務者が専用のゼッケンやエプロンを使用することで、勤務状況を一目で明らかにする仕組みを採用しています。これにより、夜勤勤務者がきちんと定時に上がれるようになり、長時間労働の解消、人件費の削減につながります。
このような取り組みを参考にし、長く安定して働き続けられる職場環境づくりを目指しましょう。
業務形態の増加
業務形態が多く、選択肢が増えれば、課題解決に向けた取り組み・働き方改革につながりやすいです。たとえば業務形態の種類は正社員や契約社員、パートタイマー・アルバイトなどが挙げられます。
正社員に固執してしまうと採用のハードルが上がってしまうため、人材不足の課題解決につながりません。介護職は未経験でも働ける仕事があることがメリットなので、非正規雇用でも働ける環境や外国人労働者を受け入れる体制も欠かせません。
深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れる在留資格「特定技能」制度、が平成31年4月1日に施行されました。
この制度により近年では、介護職の求人を出すと外国人の応募も多くなっていきています。
職員同士のコミュニケーションで難しいわかりやすい日本語を使うように心がけたり、表示が一目でわかりやすいユニバーサルデザインの機器を導入するなど、外国の方でも働きやすい環境を整えることも重要です。
IT導入による業務効率化
IT導入を積極的に行えば、業務効率化して介護職員の手間が省けます。
IT導入の事例を挙げると、介護記録ソフトの導入でペーパーレス化することで、書類作成ための残業が減少、パワーアシストスーツで介護職員の腰痛発症の低下などがあり、利便性が高いです。
また、介護ロボットの一つである見守りシステムを導入することにより、介護職員の休憩時間や介護記録作成の時間を確保ができるようになるなど、介護現場が抱える課題の解決に結び付いています。 見守りシステムには、センサータイプ、バイタルタイプ、カメラタイプと様々な種類があります。パソコンやタブレット端末などから遠隔で居室の状況を把握することが出来るため、訪室回数を少なくすることが期待できます。
しかし、介護業界のIT導入は進んでいるとはいえません。導入すれば業務効率化につながるので、未導入の施設運営者には、検討をおすすめします。 国からの補助金等を活用することでなるべく費用を抑えて導入することも可能です。
IT/ICTを導入するメリット
ITやICTの導入を積極的に行っている介護事業者もあり、業務効率化の恩恵を受けています。
ITやICTを導入することでどのようなメリットを得られるのかをご紹介いたします。
そもそもITとICTの違いとは?
ITとICTはどちらも略称で、微妙な違いがあります。
ITとは「Information Technology」の略称で、直訳すると「情報技術」です。 情報通信関連のインフラや技術、ハードウェアの制御など、コンピューターをはじめとする技術の総称が「IT」です。
対してICTとは「Information and Communication Technology」の略称で、直訳すると「情報伝達技術」です。 ITよりも情報や知識の伝達に特化した内容をICTと呼び、情報のみに限定されない特徴があります。 わかりやすく伝えると、ITは技術そのもの、ICTはインターネットを活用することで人と人をつなげる技術です。
情報の一元管理・属人化を防ぐ
IT/ICTを導入すると、情報の一元管理が可能となり、属人化を防ぐメリットがあります。一元管理とは、散らばっているいくつかの情報を一括で管理する方法で、情報が多い介護業界では大きなメリットです。手書きの記録とデータで入力する記録が分かれているのなら、積極的にIT/ICTを導入した方が良いでしょう。
属人化とは、業務の仕方や進め方などの内容を、特定の担当者のみが把握している状況です。仮に特定の介護職員が体調不良などで休んだ場合、業務の進め方がわからなくなって不安に感じる職員もいるでしょう。
しかし、ITやICTを利用すれば情報の伝達がスムーズになり、全体で情報共有が行われていると、特定の介護職員がいない場合でも対処できるようになります。
職員全員が必要な情報を閲覧できるようにすることで、電話などで情報を確認する必要がなくなり、介護サービスの利用者を待たせる心配もなくなります。また、事務作業の時間を削減することができ、その他の必要な業務の時間の確保に繋がります。
データ活用によるサービスの質の向上
IT/ICTを導入すると、データ活用によるサービスの質が向上します。
介護現場で介護サービスの利用者の情報が多く、記録するデータがたくさんあります。紙媒体で体温計や血圧計で測定した数値を記入するのもいいですが、情報が見えにくいと活用しにくいです。
そこでIT/ICTを導入して施設内の様々なシステムを連携し、1つのシステムで記録・管理を行えばデータの分析が容易になり、サービスの質向上につなげられます。現代では体温計や血圧計などで測定した数値を自動的に転送する技術や機器があり、介護現場で立っています。
サービスサイトはこちらから
今後の介護業界の展望
今後の介護業界の展望は、課題が多いものの、就労環境が徐々に改善される見込みがあります。
介護サービスのニーズは高齢化に伴って増えていくため、介護業界の将来性は高いです。介護士は無資格でも活躍できる職業ですが、働きながらスキルを磨き資格の勉強をすればキャリアアップを目指せる魅力があります。
国も2040年を展望にして、今後の介護業界が良くなるように改善を実現するのが目標です。具体的には多様な就労・社会参加の環境整備をするために、70歳までの就業支援を行います。他にも健康無関心層へのアプローチを強化するのと、地域・保険者間の格差を解消することで、健康寿命を3年以上伸ばす目標です。
参照元:厚生労働省「2040年を展望した社会保障・働き方改革本部のとりまとめ」について
まとめ
介護業界が抱える課題には、人材不足や過酷な労働環境などがあります。 要介護者の急増によって、今後の介護業界の需要は今まで以上に伸びていくでしょう。 それに伴って介護業務の負担はますます増すと予測できます。ITやICTの導入で、介護負担を軽減しましょう。